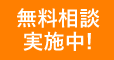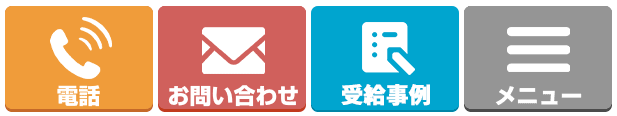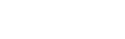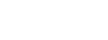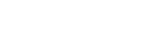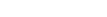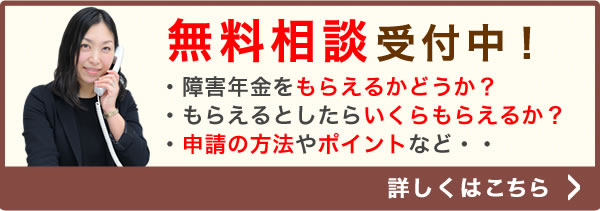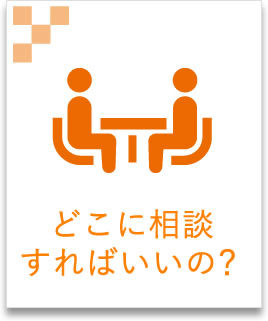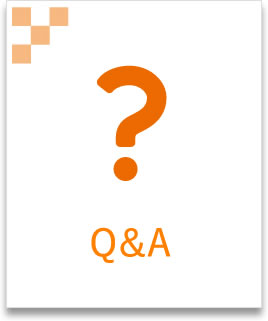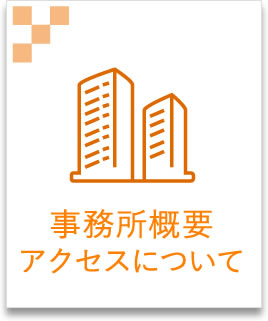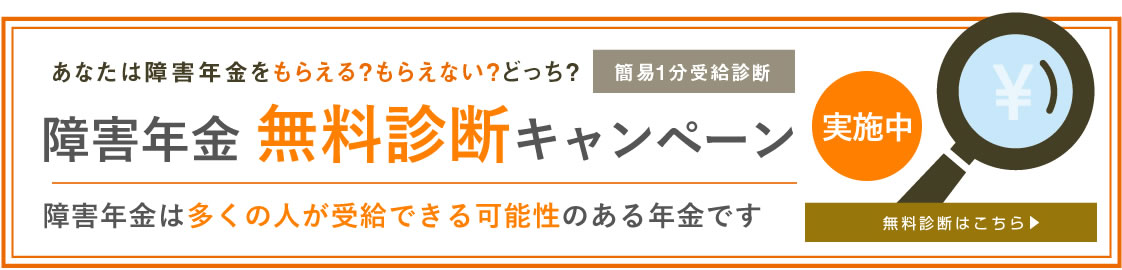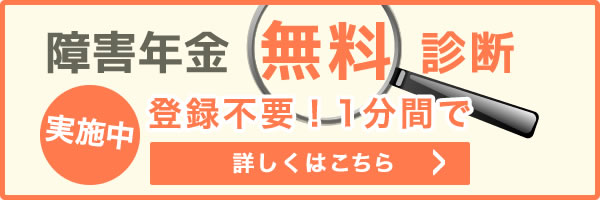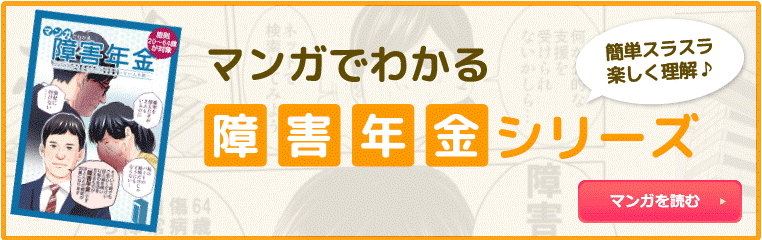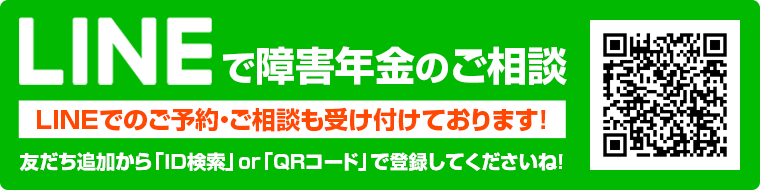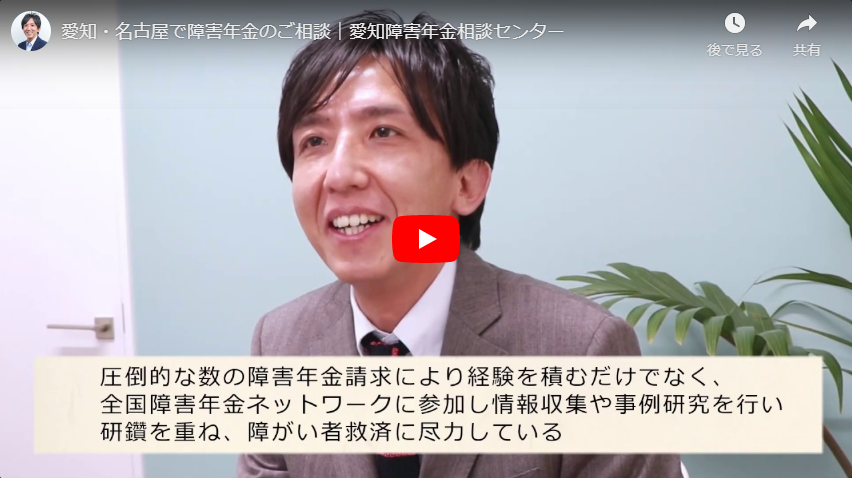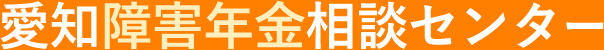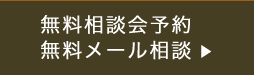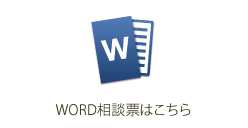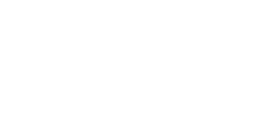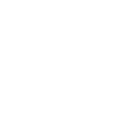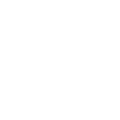大人の発達障害は障害年金の対象です。ADHD・ASDでの受給事例を紹介!
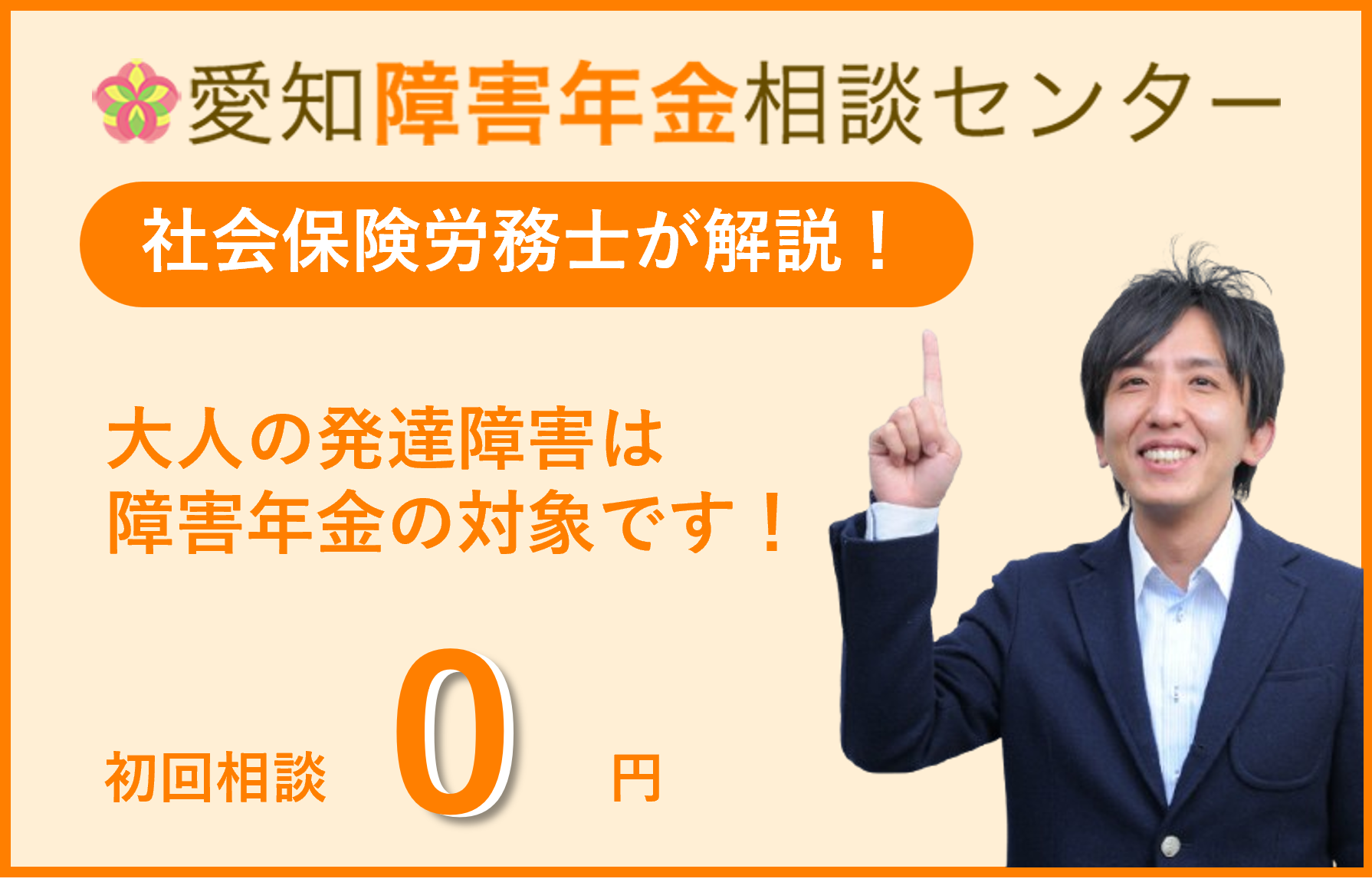
「大人の発達障害」は近年多くのメディアで取り上げられ、広く認知されるようになりました。
子どもの頃には気づかれなかった、あるいは診断されなかった発達障害(ASD:自閉スペクトラム症、ADHD:注意欠如・多動症など)が、大人になってから社会生活を送る中で顕在化し、仕事や人間関係、日常生活において様々な困難を感じている方が少なくありません。
当センターにおきましても、進学や就職以降に「他の人と同じようにできない」「コミュニケーションがうまくいかない」「集中力が続かず仕事でミスが多い」「単純なミスを繰り返してしまう」「人間関係のトラブルを頻繁に起こしてしまう」「仕事が長続きしない」といったことで思い悩み、大人になって初めて発達障害と診断された方からの相談は増えています。
もし、発達障害が原因で働くことが難しい、あるいは日常生活に大きな支障が出ている場合、「障害年金」を受給できる可能性があることをご存知でしょうか?
この記事では、大人の発達障害で障害年金の受給を考えている方に向けて、その可能性、受給のための要件、申請手続きの重要なポイントについて、障害年金専門の社労士が分かりやすく解説します。
大人の発達障害とは
発達障害とは、先天的な脳の特性です。言葉の発達が遅い、対人関係の構築が困難、集団行動が苦手、特定分野の勉学が極端に苦手など様々な症状がみられます。
発達障害は大人になってから発症するものではありません。多くの場合は子供の頃からその特性が現れています。
しかし、個人差があることや、性格や個性と捉えられ見逃されることも多く、進学や就職以降、より複雑なコミュニケーションが必要になった時に困難を抱えるようになり、そこで初めて自覚したり、診断されたりします。これを大人の発達障害といいます。
発達障害の症状
発達障害には大きく3つの種類があり、現れ方や程度には、個人差があります。
ひとつの種類だけが現れる人もいれば、複数が重なって現れる人もいます。日常生活や仕事などで支障がない場合もあれば、さまざまな困難を抱えて生きづらさを感じる場合もあります。
また、発達障害は知的障害の併発や、二次障害としてうつ病などの精神疾患を患う場合があります。
◆ADHD(注意欠陥・多動性障害)
集中力が続かない、ものをなくしやすい、期日を守れないなどの「不注意」、落ち着きがない、衝動的な感情や行動を抑えられない、思ったことを口にしてしまうなどの「多動性・衝動性」といった特性があります。
ADHDの特性は小児期から成人期まで続くことが多いですが、大人になるにつれて「多動性・衝動性」は目立たなくなる傾向があります。
一方で「不注意」は大人になっても現れやすいと言われています。また、子どもの頃は気付かなかったけれど、職場でミスを繰り返すなど日常生活や社会生活で様々な支障が出てくることにより、大人になってADHDに気付くこともあります。
◆ASD(自閉スペクトラム症)
コミュニケーションの困難さや、こだわりの強さ、興味関心の狭さ、感覚の過敏さなどの特性があります。
親密な付き合いが苦手、会話が一方的、言葉を文字通りに受け取ってしまう、融通が利かないなどの症状がみられます。
◆LD(学習障害)/SLD(限局性学習症)
知的発達の遅れや視覚・聴覚機能の問題がないにもかかわらず、「読めない」「書けない」「計算できない」「推論できない」といった特定の学習行為が極端に苦手という特性があります。
読むことが苦手な読字障害は「ディスレクシア」、書くことが苦手な書字表出障害は「ディスグラフィア」、数字や計算が難しい算数障害は「ディスカリキュリア」と、タイプによって大きく3つに分類されます。
LD/SLDは知的障害とは異なるため、子どものころは単に「勉強不足」や「努力が足りない」などといわれ見過ごされてしまうこともあります。
大人の発達障害で障害年金は受給できるか
結論から言うと、大人の発達障害(精神の障害)が原因で、日常生活や就労に著しい制限を受けている場合は、障害年金の受給対象となる可能性があります。
重要なのは、「発達障害である」という診断名だけではなく、「その発達障害によって、どの程度日常生活や仕事に支障が出ているか」という点です。障害年金は、病気やケガそのものではなく、それによって生じる「障害の状態」に対して支給されるものだからです。「大人の発達障害で障害年金を受給するのは難しい」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、要件さえ満たせば障害年金を受給することができます。
下記にて、当事務所における障害年金受給事例の一覧をご覧いただくことができます。
「自分のケースはあてはまるのか」ぜひご覧ください
障害年金の受給要件
①初診日要件
国民年金、厚生年金、共済年金の被保険者期間中に、障害の原因となった病気やケガに対して医師の診察を受けることが必要です。
この診察を初めて受けた日のことを「初診日」といいます。
なお、年金制度に未加入であった20歳前の傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。
②保険料納付要件
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の期間が以下のいずれかを満たしていることが必要です。
・保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者であった期間も含む)
・保険料を免除された期間
・学生納付特例又は若年者納付猶予の対象期間
要するに、これまでの被保険者期間のうち3分の1を超える期間で保険料の未納がないことが問われているということです。
ただし、上記の要件を満たせなくとも、令和8年3月31日までに初診日がある場合(初診日において65歳末満の人に限ります)については、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ、要件を満たしたものとされます。
なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。
③障害認定日要件
障害認定日において、一定の障害があることが必要です。
障害認定日とは、本来の障害の認定を行うべき日のことをいい、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日をいいます。
この障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、その翌月から年金が支給されます。これを障害認定日請求といい、請求が遅れても最大5年遡って支給されます。
発達障害における障害状態の目安は以下となります。
▶【3級】※厚生年金加入中に初診日がある方のみ
発達障害により、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの。
▶【2級】
発達障害により社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活に多くの援助を必要とする。
▶【1級】
発達障害により社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活に常時援助を必要とする。
障害等級の判定は障害の重さだけではなく、就労状況や日常生活状況なども考慮されます。
働きながらの受給も可能
就労の有無が重要な判定要素となるのは事実です。
しかし、障害年金における「労働能力」というのは、健常者と同じ環境下で、同じ労働ができる能力のことを言います。
就労制限(業務が限定的である、時短勤務、残業の免除など)や特別な配慮を受けている場合、または障害者雇用での就労や就労支援施設での労働は「労働能力がある」とは言えないと判定される可能性があります。
実際の業務内容や配慮の程度、雇用形態、就労状況により障害年金を受給することはできます。
下記の記事にて、働きながら障害年金を受給する際のポイントや注意点を詳しく解説しています。
障害年金の申請手続きと重要な書類
障害年金の申請には、多くの書類が必要となり、手続きも複雑です。特に重要な書類は以下の2つです。
-
①診断書
-
医師に作成してもらう、障害の状態を証明する最も重要な書類です。精神の障害用の様式があります。発達障害の特性による日常生活や就労上の困難さを、医師に正確に理解してもらい、具体的に記載してもらうことが重要です。普段の診察だけでは伝わりきらない困難さを、メモにまとめて医師に渡すなどの工夫も有効です。
-
②病歴・就労状況等申立書
-
ご自身(または代理人)が作成する書類で、発症から現在までの経過、日常生活や就労状況、感じている困難さなどを具体的に記述します。診断書を補完し、ご自身の状況を伝えるための重要な書類です。発達障害の場合、具体的なエピソード(仕事での失敗例、対人関係での困難、日常生活での支障など)を交えて、分かりやすく記載することがポイントです。
大人の発達障害における申請の難しさ
大人の発達障害で障害年金を申請する場合、以下のような特有の難しさがあります。
①初診日の証明が難しい: 子どもの頃の記録がなかったり、受診を中断していたりする場合。
②障害の程度が伝わりにくい: 外見からは分かりづらく、「怠けている」「努力不足」などと誤解されやすい特性のため、客観的に困難さを証明するのが難しい。
③医師との連携: 障害年金制度や求められる記載内容について、医師が十分に理解していない場合がある。
④書類作成の負担: 「病歴・就労状況等申立書」で、自身の困難さを具体的に、かつ論理的に記述する必要がある。
専門家である社労士に相談するメリット
障害年金の申請は、ご自身で行うことも可能ですが、上記のような難しさから、専門家である社会保険労務士(社労士)に代行を依頼する方が増えています。
社労士に依頼するメリットは以下の通りです。
①複雑な制度や手続きを熟知している: 最新の審査基準やガイドラインに基づき、的確なアドバイスやサポートが可能です。
②初診日の証明サポート: 必要な書類の収集や、証明が難しい場合の代替手段などを一緒に検討します。
③診断書作成の依頼サポート: 医師に障害の実態を的確に伝えるためのアドバイスや、必要に応じて医師面談への同行も行います。
④病歴・就労状況等申立書の作成サポート: ご本人の状況を丁寧にヒアリングし、審査で考慮されるポイントを押さえた書類を作成します。
⑤申請手続きの代行: 複雑な書類準備や年金事務所とのやり取りを代行し、ご本人の負担を大幅に軽減します。
⑥受給の可能性を高める: 専門的な知識と経験に基づき、不支給のリスクを減らし、適正な等級での受給を目指します。
まとめ
大人の発達障害で障害年金を受給することは可能です。先に説明した通り、審査では、障害の重さだけではなく、日常生活状況や就労状況なども考慮されます。
診断書の内容は非常に重要で、ご自身の状況を医師にしっかり伝えた上で診断書を作成してもらわなければなりません。
また、病歴・就労状況等申立書には診断書と相違ない内容、かつ、診断書には記載しきれない日常生活や就労状況、困難さを具体的に記載する必要があります。
障害年金の申請は制度が複雑なため、ご自身での請求は難しそうと感じられる方もいらっしゃると思います。実際に「自分で請求しようと書類を取り寄せたが複雑でわからない」とご相談いただくケースも多々あります。
その際は社会保険労務士(社労士)へのご相談をお勧めします。しかし、社労士にも得意分野がありますので、障害年金に特化した社労士であるかを見極め、サポートを依頼しましょう。
愛知障害年金相談センターでは、無料相談を行っております。予約制ですので、お電話またはメール、ラインにてお気軽にお問い合わせください。
最終更新日 2025年4月3日 by 社会保険労務士 久保将之
コラムの最新記事
- ペースメーカーを装着している方は障害年金の対象です!もらえる条件や等級基準・申請ポイントを解説
- 人工血管・ステントグラフトの挿入されている方は障害年金の対象です
- 双極性障害で障害年金を受給するには?受給条件と申請のポイントを詳しく解説
- 統合失調症で障害年金を受給するには?受給条件と申請のポイントを詳しく解説
- 【障害年金】家族が脳梗塞になったら手続きをご検討ください
- 人工透析(慢性腎不全)は障害年金の対象です。条件・認定基準・申請方法を詳しく解説!
- 障害年金の遡及請求とは?認められやすい傷病と難しいケースを紹介!
- 傷病手当金の終了後や退職後は障害年金の申請をご検討ください
- うつ病・精神疾患は障害年金の対象です【名古屋の社労士が解説】
- 働きながら精神疾患(うつ病)で障害年金はもらえる?障害者雇用とフルタイムでの違い
- 人工関節で障害年金を申請する際のポイントと受給事例をご紹介!